企画一覧
SARP企画
【展評】光と立体による空間 翁ひろみ

『(1)翁ひろみ個展「角のある形-余白」(2015.12.1-12.6)SARP』
今回の仙台sarpでの翁ひろみの個展(1)は、これまでの展示とは大きく異なる内容だった。翁の作品は、木材を組み合わせて立体を作り、その表面をアクリル石膏で半ば覆ったものが主であり、それを会場内に複数個設置するという展示形態をとってきた。
これまでは、その立体がなんらかの特徴ある形であって、観者の視線がそこに注がれることが意図されていた。

『(2)翁ひろみ個展「地球照 静かの海」(2011.7.19-7.24)SARP』
たとえば2011年の個展(2)では、床と平行するいくつもの水平な構築物を周囲の壁に設置することで、また前回の個展(3)では、会場の中心に、他と比べてかなり大きな板状の立体を立てることで、観者の意識がそこに集中することを促していた。ところが今回の展示では、比較的小さな、四角い板状とキューブ状という、無性格な二種類の立体に限定されていた。二つは、そこから特定の表象がなされるようなものではなく、それらを使って空間の中に中心的な箇所を積極的に作ろうとしているようにも見えなかった。
中心を作らないという姿勢は、具体的にいくつかの点が指摘できる。一つは、同じ種類の立体が複数個まとまって設置されている箇所が、偶数であることだ。たとえば壁には、板状の立体が縦に2枚、横に4枚と連続して置かれ、床にはキューブ状の立体が2個、板状の立体が左右の壁沿いに1枚ずつ置かれる、といった具合である。同じ形で同じ大きさの物体が、直線上に複数並べられる場合、それが奇数ならばシンメトリーが強調され中心性が生じる。だが偶数ならば、中心となる場所に物体が存在しない分、中心性は弱められる。(4)

『(3)翁ひろみ個展「地球照 新しい海」(2013.11.26-12.8)ギャラリーターンアラウンド』
中心があれば、空間にヒエラルキーが生じるが、そのような階層がなくなることで、観者は空間全体をとらえようとするだろう。
もう一つは、スポットライトによる光が、直接立体を照らしていないという点である。スポットライトは、作品を鑑賞しやすくしたり、陰影を与えて立体感を強調したりする「補助的」な存在だが、翁はこれまでも、スポットライトの光を作品の構成要素の一つとし、立体と同等の重みをそれに与えてきた。今回の展示では、その性格がより強くなっている。
画廊の正面の壁は、それを象徴しているかのようだ。この壁には、展覧会のメインとなる作品が、2~3点展示されることが多い。だが作者は、壁の中央に何も置かず、板状の立体を一枚だけ極端に右隅に寄せて設置した。そして中央の何もない場所に、余白を強調するかのようにスポットライトの光を当てたのである。物体(板状の立体)周辺は暗く、何もないところの方が明るいこの壁が示すのは、展示された物体だけが重要なのではなく、光ともども壁全体、ひいては空間全体を提示したいという作者の意識である。
壁に展示されたものの高さが一様でないことにも、その姿勢は表れている。壁に展示する場合、作品の中心を床から何cmと決めて行うことが多いが、今回そうでないのは、壁にある板状のものが、額縁をつけられた絵画のように、個別にその内側だけで完結するのではなく、周囲と呼応して存在するものだと捉えている証拠だろう。全体の中で、それが最もふさわしい場所、すなわち、それを置くことで物体自身はもとより、空間全体がより活性化する場所とはどこなのか。それは20cm上なのか5mm下なのか、左右に移動すべきなのか床に寝かせるべきなのかを、常に空間全体に立ち帰って考察した結果だということである。
今回の翁の展示は、全体を一つの空間的ヴォリュームとして提示しようという意図が伝わってくる。だが、単に抑揚のない空間が作られているわけではない。光の明暗の配置、立体の布置における粗密、この画廊空間の特徴である出隅入隅を意識した物体の配置は、適度なリズムを維持しながら行われている。とすれば、全体における抑制の効いたリズムの偏差こそが重要だろう。この方向を今後も作者が推し進めるとするならば、明らかな意味や方向性が生じる危険を回避しながら、この偏差を維持し展開する、ぎりぎりのライン取りが今後も要請されるに違いない。そのとき、たとえばアクリル石膏による立体の覆い方が、もう少し均質性を増すならば、さらにそれが先鋭化する予感がしたことを付記しておきたい。
和田浩一(宮城県美術館学芸員)
(1)翁ひろみ個展「角のある形-余白」(2015.12.1-12.6)SARP
(2)翁ひろみ個展「地球照 静かの海」(2011.7.19-7.24)SARP
(3)翁ひろみ個展「地球照 新しい海」(2013.11.26-12.8)ギャラリーターンアラウンド
(4)翁の作品は決してミニマル・アートの範疇には入れられないが、作品内部の「偶数」の件に関しては、ドナルド・ ジャッドの作品の多くがそうであることが参考となろう。

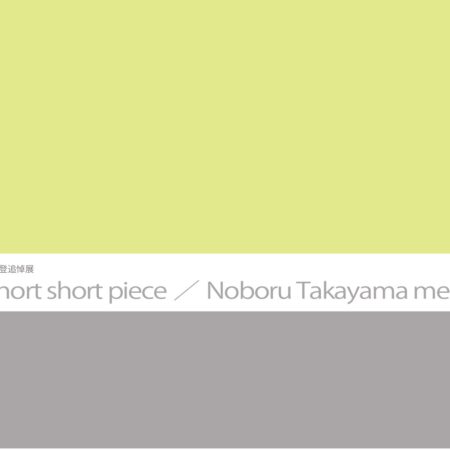


-450x450.jpg)


_page-0001-450x450.jpg)